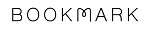「チョコレートのつつみ紙をはがすと、ぴかぴか光るぎんがみ。ぱりっとしていて、うすくて、ゆびでそっとやぶいてみれば、たちまちチョコレートのあまいかおりにつつまれて・・・・
これは、板チョコレートのクーちゃんと、なかよしのぎんがみちゃんの、とろけるようなたのしい毎日のお話です。」まえがきより。
えっ、でもちょっと待って。板チョコレートのクーちゃん?
「クーちゃんとぎんがみちゃん」 岩崎書店 2022年2月発行 80ページ
北川佳奈/著者 くらはしれい/画家
カカオの町に住む板チョコレートのクーちゃんとなかよしのぎんがみちゃん、ふたりがいかにして人間関係を構築していくか、というお話です。
クーちゃんは、リボンといった可愛いもの、おしゃれが大好き。話し方はやわらか。
対するぎんがみちゃんは、音楽が好き。可愛いものにはあんまり興味はなさそうで、語尾はさっぱりして、性格もさっぱり。
ふたりの共通項は少なめかもしれませんね。
相手への共感と反発を繰り返すことによって深まる友情の物語、8話。
たわいないやりとりですが、これがなかなかなのですよ。互いの気持ちをてさぐりあしさぐり、ふたりが距離感をはかりあっているのが面白いのです。間違いないのは、ケンカしたって、自分と違うものが好きであっても、大事にするものが違っても、相手を好きだという気持ち。とても安心して読めるのです。
若い読者は、どう感じるのかなあ、この友情物語。子どもの頃に読んだら、正直なところ、わたしはあまり面白いと思わなかったかもしれません。そこそこの年をとった今だから、親しい人の大事さを痛感し心に響いたようにおもいますので、きっと大人のかたも楽しめる本でしょう。
余談ですが、焚き火で栗を焼いて食べるシーンがあり、たまらなくおいしそう。お腹が減ります。
そして、気になる「板チョコレートの」という点について、お話いたします。
表紙の絵を御覧ください。ふたりが仲良くならんでおります。
左がクーちゃん。チョコレート色の髪、板チョコ模様のお洋服の子ですね。
右がぎんがみちゃん。金色の髪、レモン色のお洋服に、銀色のアルミカップのようにパリパリっと折り目のついたエプロンをした子です。
さし絵は、お菓子(とそれに付随するもの)を、擬人化して描かれています。
カカオの町にはほかにも、ミルフィーユショコラ、フィンガーチョコレート、ウィスキーボンボン、マーブルチョコレートなどおいしそうなお菓子、いえ登場人物たちが登場します。イラストをみると、それぞれのお菓子らしいレトロ素敵なデザインのお洋服を着ています。
(マーブルチョコ、ずいぶん食べてないなー。・・お腹をすかせてカカオの町へ行かないほうがよさそうだ。)
著者は、このような擬人化のさし絵がつけられる、とはおもってなかったのではないかしら、と想像しました。
「頭のリボンをととのえてそとに出ると~(p.7)」という文章があります。擬人化を想定していたなら、(頭の)ではなくて(髪の)と書いたのじゃないかしら。
「さっきまでやわらかくほぐれていたクーちゃんのチョコレートも、ぴっとかたくなった気がします。(p.10)」「ふりかえると、ぴかぴかわらって、ぎんがみちゃんがたっているではありませんか。(p.11)」
文章ではクーちゃんはやはりチョコレートで、ぎんがみちゃんも銀紙なんですね。それでいてさし絵は、人間の少女。チョコと銀紙の会話が擬人化と反する表現をみつけると楽しい。文とさし絵のそれぞれの表現がうまく作用して、面白さが増しているようです。
そして、クーちゃんはレモン色がすきなのですが、表紙のぎんがみちゃんのワンピースの色がレモン色ですね。すきなひとの好む色をとりこんで、同化したい気持ちをあらわしているようです。ぎんがみちゃんのマネをしたい、そんなクーちゃんの心の動きを感じます。可愛らしいじゃあありませんか!
なんともほっこりするお話でした。お気に召しましたらどうぞ手にとってみてくださいませ。
さし絵のくらはしれいさんの塗り絵があるそうです↓かわいいですね。